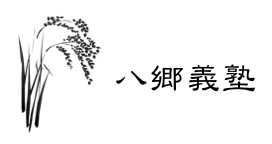
近年、会話が重視された結果、学校では文法や和訳を学ぶ機会が格段1に少なくなりました。 また、和訳を学ぶ際にも、それは意訳が中心です。 主語述語や単語一つ一つを意識していくよりも、チャント2と呼ばれる短文や句を「塊」として覚えていきます。 例えば
ただ、これは、初歩的な暗記が必要なレベルでは有用なのですが、問題が3つあります。
1つ目は暗記量が非常に増えてしまう問題です。 動詞だけ見ても、英語の動詞のパターンは最低で5つあります。 いわゆる5文型です。
色々なチャンツから、「結局はこの5つに落とし込めるのだ」と自分で気づける人は非常に珍しいと思います。 落とし込めるのだと気が付かない場合、「それは同じ/別の種類の表現だ」と認識できないので、出てくる度に覚えることになります。
かなり大量の練習や暗記が必要になるでしょう。 また、理屈が分かっていて覚えるのと、覚えた結果、自分で理屈を作り出すのでは、前者の方が遥かに楽です。
もう1つは少し複雑になると一気に破綻することです。 以下は北海道でほぼ全ての中学生が受ける模試、北海道学力コンクール(道コン)で使われた英文の一部です。 これで1文です。
I heard that more schools have introduced new uniforms that are easy to be washed and comfortable to move in, or let the students choose what uniform they will wear, such as skirts or pants.
中学範囲の英文法だけで作られていますが、 フレーズの暗記でどうにかなるものではありません。 全ての単語の意味が分かったとしても意味が正確にとれないかと思います。 中学生が苦しむであろう文法事項は以下になるでしょうか。
動詞だけでも、heard, introduced, are, be washed, move, let, choose, will wear と並んでいます。 どこからどこまでが、その動詞の及ぶ範囲なのか、文法知識なしでは大混乱するでしょう。 一文の中に中学範囲の文法事項がこれでもかと盛り込まれています。
最後が最大の問題です。 正確な和訳を試みないと、自分が何を分かっていないのかが分かりません。 何が分かっていないのかが分からないのであれば、何を覚えて良いのかも分かりません。
たとえば以下の文を見てみましょう。Here We Go 中3 Read 2 の一文です。 教科書レベルの一般的な単語の意味も付けておきます。
どうやって和訳を作れば良いでしょう。 適当な日本語を作文してはいけません。
例えばこの3つを考えずに適当な意味を取ろうとしてはいけません。 1~3のどれが分かれば、自分は正しい意味が取れるのか、それをいつもいつも考えなければいけません。 「知っているつもり」と「知っている」には大きな違いがあります。
知っているつもり、出来るつもり、分かるはずといった曖昧4さを消すために勉強するわけです。 そのためにも、適当な意訳/作文は決してしてはいけません。
文章を読む時、人は無意識に分からない部分を読み飛ばすクセを持っています。 意味がわからない部分を適当に読み飛ばし、なかったことにするくせがついています。 例えば「この記事でさえ」全部読まずに読み飛ばしたのではないでしょうか。
普段はそれで良いかもしれませんが、テストでは困ったことになります。 なぜなら「本当に読めているのか、分かっているのか」を問われることになるためです。
どんな科目の、どんな単元の問題でも、どこが分かっていてどこが分からないのか、それを特定することが最も重要です。英語においては「完全な和訳を試みること」、それが第一歩になります。