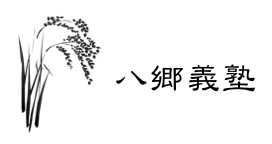
一時期、インターネット上に出回っていた文章に以下のようなものがあります。
この ぶんょしう は イリギス の ケブンッリジ だがいく の けゅきんう の けっか、 にんんげ は もじ を にしんき する とき その さしいょ と さいご の もさじえ あいてっれば じばんゅん は めくちちゃゃ でも ちんゃと よめる という けゅきんう に もづいとて わざと もじの じんばゅん を いかれえて あまりす。
読めたでしょうか。
この文章は、イギリスのケンブリッジ大学の研究の結果、 人間は文字を認識する時、その最初と最後の文字さえ合っていれば、 順番はめちゃくちゃでもちゃんと読めるという研究に基づいて わざと文字の順番を入れ替えてあります。
上記の文のように、単語の最初と最後さえ合っていれば正しく読めてしまう現象はタイポグリセミア1と呼ばれています。 タイポグリセミアに限らず、人は、ある文の一部に意味のわからない部分があっても、そのわからない部分を「経験や知識で勝手に補ったり省略して」意味を取る仕組みを持っています。
なお、タイポグリセミアについて、ケンブリッジ大学で研究された事実はありません。 いわゆる都市伝説2に近いものです。
人のこの能力は、日常生活では非常に有用なのですが、勉強の場面では非常に厄介です。 「知らない、わかっていない、読めていない」のに、自分では「読めていない」と気づけなくなるのです。
例えば、算数で文章題が苦手な小学生は、そもそも自分が文章題を読めていないことに全く気付けません。 英語が苦手な中高生は、知らない単語、知らない意味のルールを読み飛ばす自分に全く気付けません。
理科や社会でもそうです。 教科書で良くわからない部分があっても読み飛ばすので、ツギハギだらけの不思議な社会や理科が出来上がってしまいます。 でも、それは自分では全く気付けません。
問題集は、「あなたは本当にわかっていますか?、意味がとれていますか?」と問いかける存在です。 ただ、ここでも大問題が起きてしまいます。 人には読み飛ばすクセがあるのですから、問題集の設問だって読み飛ばします。
本文を読み飛ばし、設問も読み飛ばします。 これで問題集の効果が十分に上がるかといえば、上がるわけがありません。 何だか良くわからないモヤモヤした霧の中、何だかよくわからない答えを覚えているだけです。
人の、自分の自然な機能や行動に、どれだけブレーキを掛けて自覚できるかが大事です。 不自然な行動を自然にするように訓練するために勉強しているとも言えますね。
「読み飛ばしグセ」の一番簡単な確認方法は、国語であれば音読です。 意味がわからない言葉、知らない言葉を音読しようとすると、大抵の人はつっかえます。
英語であれば音読に加えて和訳です。 知らない言葉は発音すら出来ませんし、意味でさえ勝手に補ったり省略する自分に気がつくはずです。
数学であれば図示することです。 文の意味や状況を読み飛ばしていれば、絵図に起こすことも出来ません。
塾でも頻繁3に言うことです。 是非、頑張って「読み飛ばす自分」に気づいて修正していきましょう。