三重県後期選抜の仕組み
高校入試の仕組みは各都道府県ごとに違います。特に調査書(内申書)の取り扱いが異なります。三重県の仕組み(後期選抜)についてになります。
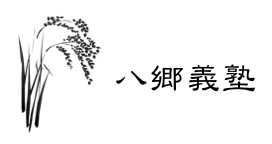
坂の向こうにはまた坂があるのかもしれない。海なんかないのかもしれない。そもそも海を見たかったのかどうかも分からない。
受験を前にすると誰しもそんな不安で一杯になります。でも、一人では苦しいことも、誰かとなら続けられることも多くあります。そのお手伝いができれば幸いです。
高校入試の仕組みは各都道府県ごとに違います。特に調査書(内申書)の取り扱いが異なります。三重県の仕組み(後期選抜)についてになります。
コツコツ積み重ねることが大事、とよく言います。ただ、「積み重ねる」とはどういうことでしょう?
教科書にも問題集にもどんな本にも必ずあるもの、それは目次です。特に受験生は目次を上手に使いましょう。
問題集に取り組むのは当然有効な勉強法ですが、問題集なしに勉強することも必要です。その際、重要になるのは歴史という科目の枠組みです。
もう県立高校入試まで時間がなくなってきました。入試に限らず、期限のある勉強や仕事は多いものです。その際、逆算で管理することも覚えましょう。
地理の勉強では、問題集に頼るばかりではなく、地図を自分で書いてみましょう。綺麗な地図ではなく、用の足りる地図です。
この地域の英語採択教科書である Here We Go はかなり従来とは異なる作りをしています。一旦苦手になると非常に回復が難しいものになっています。
やる気がある、やる気がない、勉強ではしばしば問題になることですが、実はやる気というものは余り大事なことはありません。
中1数学でも小5算数でもおうぎ形は習います。2回するわけですが、その2回の両方で大事なのが「割合」です。
割合が苦手な小中学生は非常に多いです。多いのですが、それはある非常に簡単な感覚がないためです。その感覚をまずつけましょう。
勉強と言えば問題集!、という思い込みをやめましょう。勉強は自分が知っているか知らないのかを確かめることです。
「結果を要求される」ということが、最初に目の前に現れてしまう年代です。公立でずっと進むには、もっとも大切な時期だと考えています。
いわゆる少人数クラス編成です。個別/家庭教師 (1対1) や大規模集団(40人規模) 講師を経験してきましたが、一長一短あり 5-10人の集団授業+個別が最も良いと考えます。
最も大事であるのは「習得」すること。技術と同じです。そのために必要であるのは「少しずつ段階を踏む / 場合によっては遡る」こと。そのため、補習は個別です。
大人は誰でも知っていますが、知識や技術の習得は「楽しい」ものです。今までも質問攻めにされてきましたし、これからも質問攻めにされたいと願っています。
祖父が千代田町の出身で、お寺様も広永町です。教育支援産業に二十年たずさわってきました。主に英語, 国語, 数学を責任担当となることが多いのですが、個人的には理科が好きで 80人規模の理科実験教室を担当したり、小学校や幼稚園へ出前実験にいったり、テレビ(ケーブルテレビ) で低年齢対象の実験番組を行ったこともあります。先生の先生なども頑張ったりしつつ、2014年 八郷義塾を立ち上げました。